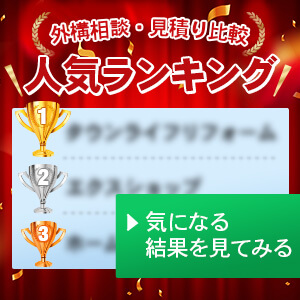こんにちは。ドライテックマガジン編集部です。
今回は「ドライテックの厚みはどれくらい確保すればいいの?」という質問にお答えします。
初めてドライテックを施工する職人の方から、ドライテックの厚みはどれくらいとればいいのか?といった質問を頂きますが、基本的には土間コンと一緒と考えてOKです。
ただ、DIYでやろうと考えている一般の方などもいますし、現場の状況によって基本の厚みも変わってくるのでちゃんと説明をしないといけないと思い今回記事にしました。
本記事ではドライテックの厚みについて、またドライテックの施工の注意事項も合わせて解説していきます。
ドライテックの厚みについて

基本的に土間コンと一緒です。
乗用車程度(3トン以下)の乗り入れの場合は、10cmの厚みが基本です。
3トンクラス(2tダンプ程度)の乗り入れがある場合は、15cmの厚みを基本としてください。
また、人のみ(車の乗り入れがない)の場合でも、最低8cmの厚みは確保するようにしてください。(そり割れの原因になるため)
転圧すると沈むので、厚みは2cm大目にとる
ただドライテックは、仕上げにプレートなどで転圧をすると大体2cmくらい沈みます。
なので、基本の厚み+2cm大目にとるようにしましょう。
乗用車程度(3トン以下)の乗り入れの場合は、基本12cmの厚みをとってください。
ドライテックの下地の厚み
ドライテックの下地は、砕石やRCなどで10cm以上の厚みで敷いて路盤をつくってください。
勾配があるところで施工する場合は、透水した水によって下地が下へ流れ出る可能性もあるので、下地の上部をセメントなどで固めると良いです。
地面の掘り下げ(鋤取り)の深さ
ドライテックを流し入れる箇所の地面の掘り下げ(鋤取り)については、下地分+基本の厚み+転圧時の沈みを考えて行います。
なので、乗用車程度(3トン以下)の乗り入れのある箇所で敷く場合は、下地分(10cm)+基本の厚み(10cm)+転圧時の沈み(2cm)=22cmの深さを目安にすると良いですね。
型枠は厚み以上のものを
地面の掘り下げ(鋤取り)したら、ドライテックを流し込むための型枠を作りますが、必ず高さは全体の厚み以上をとること。
乗用車程度(3トン以下)の乗り入れのある箇所で敷く場合は、22cm以上のものを用意すること。
高ささえあれば、材料はどんなものでも構いません。
施工後の車の乗り入れについて
施工後、車の乗り入れが可能になるまでは約1週間後が目安です。
なので、型枠の撤去や後片付けなどもその時で構いません。
まとめ
今回はドライテックの厚みについて解説しました。
施工する現場によって車の乗り入れなどの状況が違うので、本記事を参考にしてみてください。
また、ドライテックを扱う場合の作業員数の目安についてですが、駐車場1台分くらいの広さ(15㎡)であれば、知識と道具があれば1人~2人でも施工は可能です。
ただ広さが大きくなるほど人員は必要です。
もし50㎡程の広さがあるとしたら、最低4人の作業員を確保したいところ。
また、最低でも1人はアスファルト舗装工事などの経験がある方を作業員として入れておくと間違いないです。
それでは今回は以上です。
外構工事を安くするなら比較見積もりを取りましょう!
外構工事・エクステリア工事は、一般の人であれば人生に一度か二度経験するくらいのこと。そのため知識がないのが普通です。
そのため一社の言いなりになって話を鵜呑みにしてしまうと、相場よりも高い買い物になってしまう危険もあります。
そこでおすすめなのは比較見積もりを取ることです。
比較見積もりを取ることで、2社であれば優劣が分かり、3社以上で平均相場が分かってきます。
確かに、手間と労力がかかりますが、業者選びや金額に後悔のないよう比較見積もりを取ることを推奨しています。
>>【無料】外構相談比較ランキングを見て優良業者さんを紹介してもらう
-

-
【プロが厳選】外構相談・見積もり比較サイトランキングTOP5
【PR】 外構相談・比較ランキング 外構プラン・設計歴10年以上のプロの外構業者監修のもと、見積比較サイトを徹底比較!無料で見積もりプランを作成してもらえるサイトを厳選しました。 外構・エクステリアの ...
続きを見る