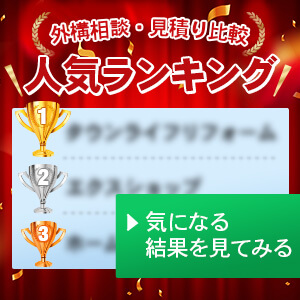「洗車中の水が隣の家に流れていってしまい、苦情を言われてしまいました。隣の家には排水溝がないため、苦情を言われてしまった感じです。洗車中の水をせき止める方法って何かありますでしょうか?」
そんなお悩みにお答えします。
ご近所トラブルで何かと多いのが、洗車中の水の排水についてです。
隣の家に排水溝がなかったり勾配が取れていなかったりすると、洗車の水や泡が流れていってしまい苦情の元となってしまいます。
そこで今回は、洗車中の水をせき止める方法についてまとめました。
ご近所トラブルを回避したい方はぜひ参考にしてみてください。
洗車の水をせき止める5つの方法
洗車の水をせき止める方法は、おもに下記の5つがあります。
- 節水コーティングセットを使う
- フクピカを使う
- 土嚢を使う
- 洗車場に行く
- ドライテックにする
それぞれ説明していきます。
1. 節水コーティングセットを使う

引用元:Amazon
まず最初にご紹介したいのは、「節水コーティングセット」を使用する方法で、洗剤・噴霧器・バケツ・スポンジ・クロスがセットになっています。
使用する水は、噴霧器に入れて車体に噴射する水と、スポンジやクロスに水を含ませるためにバケツに入れる水のみです。
特殊なクロスを使用するので、多くの水を使用しなくても車体の表面の汚れを落とすことができるというメリットがあります。
ただし水を使用しないわけではないので、車の汚れ具合などによっては多くの水を使用してしまい、隣近所に流れる可能性があるというデメリットがあります。
2. フクピカを使う

引用元:Amazon
水を使用せずに洗車する方法として、「フクピカ」という商品を使用する方法があります。
「フクピカ」は、何と言っても全く水を使用しないので、近所迷惑になる洗車の排水が発生しないというメリットがあります。
デメリットは一回使用したら終わりであることと、使用後にゴミが発生することなどがあります。
3. 土嚢を使う

洗車の水をせき止める方法として、土嚢を使うのも効果的です。
古典的な方法ですが、多くの水が発生しても流れをせき止めることができ、自分の積みたいように土嚢を配置できるメリットがあります。
せき止めた水はドライワイパーを使用して集め、流したい方向に排水すると近所迷惑になりません。
一方で、土嚢を運んで積むことはかなりの重労働で、流れる水をせき止めるには土嚢の数もそれなりに必要なことがデメリットです。
4. 洗車場に行く

洗車場に行って洗車すれば、近所迷惑を考えることなく大量の水を使用して洗車できます。
洗車場での洗車は、汚れが酷い場合でも多くの水を使用してしっかり洗車できるというメリットがあります。
一方で、洗車をするために洗車場まで移動しなければならないことがデメリットです。
5.ドライテックにする
ドライテックとは、特殊な材料を配合した新しいタイプのコンクリートです。
なぜコンクリートの一種なのに洗車の水をせき止められるかというと、ドライテックには透水性があるからです。
普通のコンクリートは水を通さないため、通常は水勾配がつけられているので水を使用すれば流れてしまいます。
ところがドライテックは、水を使用しても地面に水がしみ込んでいくので隣近所に流れていきません。
この透水性のおかげでドライテックには水勾配をつける必要がなく水平になっているため、洗車のような作業もしやすいのです。
またドライテックは、透水性のおかげで水たまりができないため快適に作業できます。
さらにドライテックは表面がざらついているので、水に濡れても滑りにくいというメリットも。
普通のコンクリートは表面が滑らかなために、水に濡れると滑りやすく転倒の危険性もありますが、ドライテックならばそのような危険性が低くなります。
このようにメリットがたくさんあるドライテックですが、デメリットもあります。
既に普通のコンクリートが打設されている状態でドライテックを利用したい場合は、コンクリートの解体から始めなければなりません。
コンクリートの解体にはかなりの費用がかかるため、予算が限られている方にはおすすめできません。
まだ舗装されていない状態でこれから庭や駐車場を整地する予定の方は、最初からドライテックにすることがおすすめです。
以上のように、洗車の水をせき止めたり排水そのものをなくす方法があるので、ご自分に合った方法でトラブルを回避してくださいね。
無料で効率的!外構・エクステリアの見積もり金額を下げるコツ

外構・エクステリア商品を買うことって人生で一度か二度あるかないか。
普段から意識してチェックしてるわけでもないから、相場価格や費用感は分からないですよね。
そんなあなたのために「見積もり金額を下げるコツ」を紹介します。
以下の通りです。
欲しい商品・工事プランが決まっている場合
「○○(商品名)は何%OFFで購入できますか?」
「○○(工事名)の実績は過去にありますか?」
欲しい商品・工事プランが決まってない場合
「○○(フェンスなど)で一番安くできる商品は、いくらぐらいで、何%OFFですか?」
「○○(工事場所・手法)の対応はされていますか?」
上記のように、複数の業者に問い合わせてみてください。
この質問で比較見積もりをすることで、効率的に最安値の価格に近づけることが可能です。
メーカー商品はどこで買っても品質は一緒です。販売価格や工事単価が業者によって違うだけだからです。
とはいえ、「そんないくつもの業者に問い合わせするのは面倒!」という方は、無料で優良業者をカンタンに検索できるサービスがあるので利用してみてください。
>>【無料】外構相談比較ランキングを見て優良業者さんを紹介してもらう
-

-
【プロが厳選】外構相談・見積もり比較サイトランキングTOP5
【PR】 外構相談・比較ランキング 外構プラン・設計歴10年以上のプロの外構業者監修のもと、見積比較サイトを徹底比較!無料で見積もりプランを作成してもらえるサイトを厳選しました。 外構・エクステリアの ...
続きを見る
外構やエクステリアのお買い物は一括見積もりがおすすめな理由
価格を安くできて、優良業者が見つかるからです。
外構やエクステリアのお買い物は、一般の人であれば人生に一度か二度経験するくらいのこと。そのため知識がないのが普通です。
だから後悔しないよう、価格を安く、かつ失敗しない外構にするには業者選びは慎重に。
そのため1社だけではなく複数業者に相談することを強くおすすめします。
前述したサイト「外構相談比較ランキング」は、厳しい審査をクリアした優良業者のみ登録しています。そのため悪徳業者は完全に排除されています。
地域によっては登録業者が少ないこともありますが、悪徳業者に当たることはまずないので安心してください。
実際にサイトを見て頂ければ分かりますが、大手ハウスメーカーから地元の工務店まで幅広く、新築外構にも対応しています。
また一括見積もり依頼は1分で終わります。必要最小限の項目だけでOKです。
自分で調べて1件1件問い合わせる、車で業者さんを周るといった、業者さん探しの手間が圧倒的に省けます!
それに業者探しの手間が省けると、商品やプランの検討に時間が使えるようになるので、外構に失敗する可能性は低くなります。
業者選び、商品選びとやることも多くなると、結局の目的は何だったのか見失ってしまうことも。。。そんな心配もなくなりますね。
一括見積もりは「検討段階」でもOK
「注文するかどうか分からない」といった、とりあえず考え中の段階でも大丈夫です。
業者側もそうした相談が多いことは分かっているので、丁寧に相談に乗ってもらえます。
特に新築の場合は考えることも多いですからね。新築の場合は備考欄に「新築外構」と入れることで得意な業者さんを紹介してくれます。
一括見積もりなら最安値で業者が探せる
そして何といっても一括見積もりの最大のメリットなのが、「価格が安くなる」ことです。
業者によって、エクステリア商品・工事費用に差があるからです。
比較見積もりを取ることで、2社であれば優劣が分かり、3社以上で平均相場が分かってきます。
実際の現場訪問しての見積もりは2社でも問題ないですが、事前の費用や割引率などの確認は、できるだけ多くの業者さんから取ることをおすすめします。
例えば価格の大きいカーポートやフェンスなどは、相見積もりで割引率が5%しか違わなかったとしても、金額の差にすると2~3万円も変わってきます。
見積もりと1~2時間の打ち合わせで、この先10年~20年使うお庭が決まってしまうので、ここで手を抜くのはもったいないです!
>>【無料】外構相談比較ランキングを見て優良業者さんを紹介してもらう
-

-
【プロが厳選】外構相談・見積もり比較サイトランキングTOP5
【PR】 外構相談・比較ランキング 外構プラン・設計歴10年以上のプロの外構業者監修のもと、見積比較サイトを徹底比較!無料で見積もりプランを作成してもらえるサイトを厳選しました。 外構・エクステリアの ...
続きを見る
上記のサイトは新築外構にも対応しているので、新築外構の相談の方もお気軽に申し込んでくださいね。
ちなみに入力は1分程度でサクッと完了します。外構についての要望が頭の中にある状態で一緒にやっておきましょう。
>>【無料】外構相談比較ランキングを見て優良業者さんを紹介してもらう